
遺産分割調停の流れや申立書、必要書類について、調停の経験豊富な弁護士が詳しく解説します。
また、遺産分割調停を申し立てると、どのくらい費用がかかるのか、弁護士費用を含め、ご説明いたします。
目次
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、遺産の分割について共同相続人の間で協議が調わないときや、協議をすることができないときに用いられる手続きです。
具体的には、家庭裁判所において、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料などを提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指す話し合いが進められます。
調停を行う機関は、原則として裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会ですが、実際に当事者双方から事情を聴くのは2名の調停委員です。
調停委員は、社会生活上豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人から選ばれます。
原則として40歳以上70歳未満で、弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士などの専門家のほか、地域社会に密着して活動してきた人などから選ばれています。
相続人同士では遺産の分け方がなかなか決まらない場合もあるので、遺産分割調停の手続きを用いて調停委員に間に入ってもらい、分割方法をスムーズに決められるよう助言してもらったり、解決案を提示してもらったりします。
遺産分割調停の手続きには、相続人全員が参加しなければなりません。
そのため、相続人の中に判断能力がない方がいれば、成年後見人の選任の申立てを行ったり、行方不明の方がいる場合は、不在者財産管理人の申立てを行ったりしなければならないケースがあります。
このような場合は、弁護士などの専門家に相談し、調停手続きをとることができるよう、しかるべく手続きを行うようにしましょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
調停委員とは
調停委員は、以下の任命基準でいずれかに該当する人材であり、人格見識の高い40歳以上70歳未満(例外あり)の者とされています。
- 弁護士の資格を有する者
- 民事か家事の紛争に対して有用な専門知識を有する者
- 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者
※調停委員は2名1組で、ほとんどの場合、男性1名・女性1名のペアとなります。
調停委員には、特別な資格は必要ありません。
もちろん、弁護士や司法書士など、普段から遺産分割の業務に従事している専門家が調停員となる場合もありますが、公的機関に勤めていた方や民生委員の方など、経歴は様々です。
そのため、調停委員に遺産分割の知識がなくとも誤った方向に進まないように、調停では弁護士を代理人にすることも検討しておくのがよいでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
審判との違い
家庭裁判所では、遺産分割調停・遺産分割審判の両方が取り扱われます。
遺産分割調停は、審判官(裁判官、1名)、調停委員(2名)で構成される調停委員会が、当事者双方の話を聞きながら進める手続きです。
調停が成立するためには、原則として、遺産の分け方について相続人全員の同意が必要となります。
遺産分割審判は、審判官(裁判官、1名)が審理を進め、当事者間での話し合いの結果や、当事者が提出した自らの主張をまとめた書面・資料に基づいて、遺産を分割する内容の審判をします。
審判は、通常の裁判の判決と同様に、当事者の同意なく下すことができます。
異議のある当事者は即時抗告を行い、高等裁判所にて再度審理・判断してもらうことができます。
なお、遺産分割調停が不成立となった場合、自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割調停を経ずに遺産分割審判を申し立てることも可能ですが、ほとんどのケースでは、「付調停」といって、裁判所の職権で調停に付される(遺産分割調停の手続きから始める)こととなります。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
訴訟との違い
調停と訴訟の違いについて
訴訟は、証拠で事実の有無を確定させ、裁判所の判断により結論を下すという手続きです。
調停は、あくまで当事者での話し合いの場であり、当事者全員が同意しないと解決ができない手続きとなります。
遺産分割の場合は、家族の問題でもあるので、調停や審判という形で解決が試みられ、遺産分割そのものについては訴訟による解決を図ることはできません。もっとも、遺産分割の前提となる事実に争いがある場合(遺言の有効性や、遺産の範囲に争いがある場合など)は、訴訟による必要があります。
申立てにかかる費用も、調停の方が低く抑えられることが多いです。
遺産分割調停では、調停成立時に遺産の分け方が確定しますが、訴訟では、控訴期間(判決正本が送達された日の翌日から起算して2週間)が経過してから判決内容が確定します。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
訴訟と審判の違いについて
訴訟は、先に説明したとおり、裁判所が判決によって結論を下す手続きであり、当事者が提出した証拠によって事実の有無を判断していきます。
審判は、裁判所の判断により結論を下しますが、当事者が提出した証拠のみならず、職権で自ら調査をして事実の有無を判断することもできます。
訴訟は、請求金額などに応じて印紙代がかかり、申立てにかかる費用が高くなる場合がありますが、審判の申立て費用は一律で、訴訟に比べ費用も低くなることが多いです。
審判も訴訟も、それぞれ異議の申立て期間(審判書/判決正本が送達された日の翌日から起算して2週間)が定められています。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
調停が行われるケース
遺産分割調停は、以下のようなケースで必要となることが多いです。
相続財産の中に不動産があり、評価額について相続人間で意見が異なるケース
相続財産に自宅が含まれる場合のほか、収益物件・借地などがある場合、評価額をめぐって争いとなることがあります。
連絡が取れない相続人がいるケース
被相続人と前妻との間に子どもがいるケースや、被相続人に子どもがおらず兄弟が相続人となるケースなどでは、相続人間での話し合いが難しくなります。
被相続人の介護をした相続人がいるケース
被相続人を介護していた相続人が「寄与分」を主張することで、なかなか遺産の分け方が決まらない場合があります。
被相続人から生前贈与を受けた相続人がいるケース
被相続人からの生前贈与を、遺産分割の際にどう評価するのか(「特別受益」など)をめぐって争いとなることがあります。
ほかにも、相続人の人数が多いケースや、相続財産が複雑であるケースなどで遺産分割調停が必要となることが多いです。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
遺産分割調停を行うメリット

調停委員(第三者)が間に入ることで話し合いがスムーズに進むことも
相続人同士の話し合いだと、どうしても私情が入り、感情的になることも多いです。
これに対し、遺産分割調停では、当事者はそれぞれ調停委員に自分の主張を伝えることになり、基本的に顔を合わせることはありません。
そのため、遺産の分け方について落ち着いて話を進めることができ、相続人同士で話をするよりもスムーズに遺産の分け方が決まることも多いです。
財産目録や遺産に関する資料などが開示されやすい
相続人同士で遺産分割を進めようとすると、なかなか相続財産の目録が開示されなかったり、生前贈与に関する資料が提出されなかったりすることがあります。
しかし、遺産分割調停の手続きでは、調停委員が、遺産の確認や特別受益などの有無について整理したり、適宜資料の開示を求めたりするため、財産内容や特別受益の有無などについて資料が開示されることが多いです。
相手方が資料をなかなか開示してくれず、遺産分割協議が進まない場合は、遺産分割調停の申立ても検討するとよいでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
民法などの法律にもとづいて(法定相続分など)話が進む
遺産分割調停では、法定相続分や特別受益など、原則として法律に沿った形で話が進められます。
法律のルールを無視して「長男が全て相続する」などと主張する相続人がいる場合には、遺産分割調停の申立てを行い、調停委員から法律を説明してもらうことで、スムーズに話し合いが進むこともあります。
遺産分割調停を行うべきタイミング
遺産分割調停は、「相続人同士だと話し合いすらできない」、「相続人同士では遺産の分け方がなかなか決まらない」という場合に申立てを検討しましょう。
相続人同士だと話し合いすらできない場合には、早めに遺産分割調停を申し立てて、調停内で話し合いを進めていくようにしましょう。
また、相続人同士では遺産の分け方が決まらないという場合には、「何回か話し合いの機会をもっても遺産の分け方についての考え方が相続人間で大きく異なる」というときに、遺産分割調停を申し立てるようにしましょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
調停を有利に進めるためのポイント
裏付け資料を提出する
遺産分割調停では、自分の主張をうまく調停委員に伝えることがポイントとなります。
具体的には、ただ単に主張を述べるだけではなく、裏付け資料も提示したうえで、主張を書面化して提出することが重要です。
例えば、相続財産の中に不動産や非上場株式がある場合は、評価額に争いが出やすいため、裏付けとなる資料とともにその評価額を主張していく必要があります。
また、特別受益や寄与分の主張については、主張する側が証明する必要があるため、証拠資料を提示しながら進めていくことになります。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
自分の主張を簡潔にまとめておく
遺産分割調停は、基本的には1回の期日が約2時間となっています。
当事者は交互に調停委員と話をするため、自分の主張がまとまっていないと、本当に伝えたいことが伝えきれずに、期日が終了してしまうということも多いです。
そのため、調停委員に自分の考えを時間内にうまく伝えられるか自信のない方は、なるべく自分の意向を書面にまとめたうえで調停委員と話をするとよいでしょう。
必要かつ的確な資料を開示する
遺産分割調停では、調停委員から資料の提出などを求められる場面も少なくありません。
提出を求められた資料の開示を拒んだり、重要な資料を隠していたことが後から発覚するなどした場合は、相手方や調停委員の心証が悪くなるため、適切に対応するようにしましょう。
資料を開示すべきか分からない、資料をどこまで開示すべきか分からない場合は、弁護士に相談して対応するとよいでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
遺産分割調停の手続きや必要書類

それでは、なかなか遺産の話し合いがまとまらず、遺産分割調停の手続きを用いたい場合は、どうすればよいのでしょうか。
ここからは、遺産分割調停の申立方法について説明します。
遺産分割調停の申立ては、申立書を作成し、必要書類を添付したうえで、家庭裁判所に提出します。
主な必要書類や提出先は以下のとおりです。
必要書類
- 申立書(相手方の人数分の写しも必要です)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票(廃棄済の場合は戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本(発行から3か月以内の原本)
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券の写しなど)
※被相続人の戸籍謄本については、法定相続情報一覧図で提出の省略ができる場合もあります。申立先の裁判所に、法定相続情報一覧図の提出での省略が可能か確認するとよいでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
提出先
当事者が合意した家庭裁判所又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
※相手方が複数いる場合は、相手方のうち1名の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てが可能です。
相手方
申立人以外の法定相続人全員
※相続分の譲渡がなされている場合は、譲渡をした相続人は、遺産分割調停の相手方とはなりません。ただし、相続分譲渡証書を作成する必要がありますので、譲渡をして調停の当事者からは外れたいという場合は、弁護士に依頼をして相続分譲渡証書を作成してもらうようにしましょう。
参照:裁判所HP
手続きの流れ
家庭裁判所に対し、調停の申立てを行うと、裁判所において、必要書類に漏れがないかなどのチェックを行います。
書類などに漏れがなければ、調停の第1回目の期日が決まり、裁判所から相手方にも申立書や期日を知らせる書類が送達されます。
申立てから、通常1~2か月程度で、第1回の期日が設けられることが多いです。
申立てをすればすぐに期日が開催されるというわけではありませんので、相続税の申告期限などがある場合は、なるべく早めに申立てをするようにしましょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停の主な流れは、以下のとおりとなります。
- 遺産分割調停の申立て
申立人が、申立に必要な書類を収集・作成したうえで、家庭裁判所に申し立てます。 - 調停期日の開催(3~10回程度が多い)
家庭裁判所にて期日が開催されます。 - 調停成立/不成立
調書が作成されます。
遺産分割調停の申立て
遺産分割調停は、
- ①申立て → ②調停期日 → ③調停終了(成立/不成立)
の流れで進みます。
①申立てには、書類の収集や申立書の作成が必要となりますので、弁護士に依頼をする場合は、①の申立て前に依頼をするとよいでしょう。
②の期日では、弁護士と面談を重ね、主張書面の作成や裏付け資料の収集などを行ってもらい、自分の主張がしっかりと調停委員や裁判官に伝わるようにしてもらいましょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
第1回目の調停期日
1回目は、調停委員から当事者に対し、担当する調停委員の自己紹介や、遺産分割調停の手続きについての説明があったり、調停申立てに至るまでの経緯の聴取が行われたりします。
第2回目以降の調停期日
第2回目以降の調停期日は、以下の流れで進むことが多いです。
- 相続人の範囲の確認(誰が相続人か)
- 遺産の範囲の確認(被相続人の遺産は何か)
- 遺産の評価の確認(被相続人の遺産の評価額はいくらか)
- 特別受益、寄与分の主張の確認(特別受益や寄与分の主張はあるか)
- 遺産の分割方法の協議(どのように遺産を分けるか)
上記①~⑤の順序で確認・協議が行われ、それぞれについて合意ができるまで、あるいは、合意が成立する見込みがないと判断されるまで、調停期日を繰り返します。
並行して、当事者双方は、上記①~⑤に関する主張書面や、裏付け資料などを提出します。
調停委員は、双方の話を聴取したり、書面の提出を促したりします。
上記①~⑤について、5~10回の期日が開催されることが多いです。
一般的に、調停期日は、1回約2時間にわたって行われ、1~2か月に1回の頻度で開催されます。
裁判所では、申立人と相手方の待合室は別室ですし、調停委員と話をするときも交互に調停委員がいる部屋まで行くため、基本的に顔を合わせることはありません。
ただし、同じ意見の相続人がいれば、複数人の相続人が同席の上、調停委員と話をすることもあります。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
調停成立・不成立
調停期日を経て、相続人全員が上記①~⑤の全てについて合意をすれば、調停が成立します。
調停が成立すると、裁判所が調停調書を作成してくれるので、その調書を用いて、不動産の登記手続きや預貯金の払戻手続きなどを行います。
合意しない場合や、これ以上協議を続けても合意が成立する見込みがない場合には、調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
遺産分割調停にかかる費用
申立時にかかる費用
遺産分割調停申立てには、被相続人1名につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代がかかります。
連絡用の郵便切手は各裁判所によって決まっているので、申立先の裁判所に確認するとよいでしょう。
(東京家庭裁判所の場合、100円×10枚、84円×10枚、50円×20枚、5円×10枚、2円×10枚の合計3310円、相手方が10名増すごとに3310円が追加となります。)
上記以外に、申立書に添付する財産資料の取得費用などがかかります。
遺産分割調停中にかかる費用
遺産分割調停の中で、裁判所が不動産や非上場株式の鑑定評価を行う場合は、当該鑑定費用を調停の当事者が負担することになります。
不動産の鑑定については、1物件あたり40~100万円程度のことが多く、鑑定の前に予納する必要があります。
鑑定費用は法定相続分に応じた負担となることが多いですが、負担割合の判断は裁判所に委ねられています。
上記以外に、財産調査などの費用がかかります。
弁護士に依頼する費用
Authense法律事務所では、遺産分割協議プランをご用意しており、着手金330,000円(税込)、報酬金は得られた経済的利益の11%(税込)でご案内しています。
初回の法律相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
弁護士を頼まずに遺産分割調停ができるか
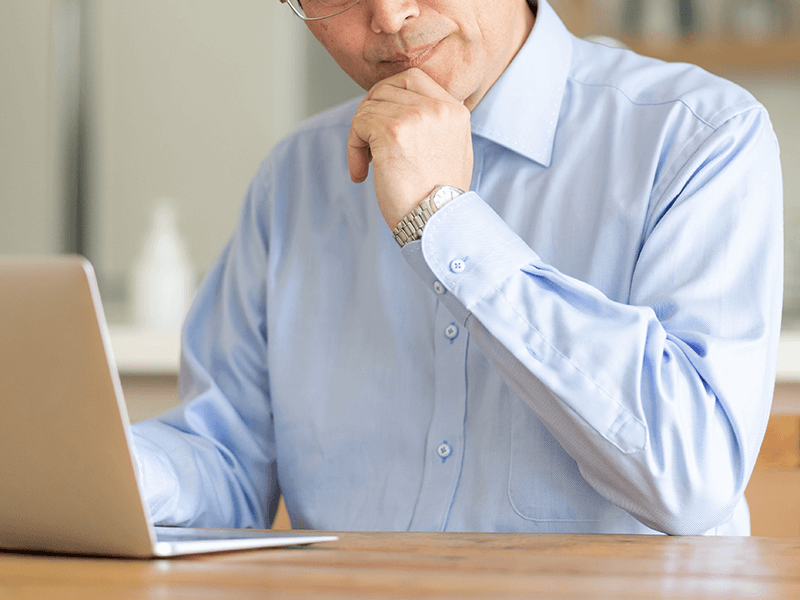
遺産分割調停にあたり、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
しかしながら、遺産分割調停では、裏付け資料を提出したり、自己の主張をまとめた書面を提出したりする必要があります。
自分だけで手続きを行う場合、せっかく伝えたいことがあっても調停委員にうまく伝えられない、証拠資料があれば認められる主張も証拠資料を提出していないので認められないなど、自己に不利な判断がなされる可能性があります。
遺産分割調停は、弁護士に依頼しなければならないということはありませんが、やはり経験豊富な弁護士に依頼した方がスムーズに進むことは間違いないでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停を弁護士に依頼すると、申立書の作成や調停期日の出廷、主張書面の作成などを弁護士が代わりに行います。
特に、自己の主張を裏付け資料をもって書面化するということは、慣れていないと難しいため、弁護士に依頼して作成をしてもらった方が調停委員会にも自己の主張が伝わりやすくなるでしょう。
また、裏付け資料の収集についても、弁護士にアドバイスしてもらいながら進めた方がスムーズです。
調停期日も1回で2時間程度ですので、自己の主張を時間内にうまく伝えるためにも、弁護士に書面を作成してもらったり、説明を補助してもらったりするとよいでしょう。
遺産分割調停は、一生のうち何度も経験する手続きではないため、慣れないことが多く、ストレスが溜まることもあります。
経験豊富な弁護士のサポートを受けることにより、手続きに対するストレスなどの軽減も期待できるので、遺産分割調停を検討する場合、まずは一度弁護士に相談されるのがよいでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
遺産分割調停後、申立が成立した場合
遺産分割調停が成立したら、裁判所が「調停調書」を作成します。
調停調書は、遺産分割についての合意内容が反映された書面で、この調停調書を用いて相続登記や預貯金の名義変更などの相続手続きを行います。
このことから、調停調書の記載方法が誤っていると相続登記や名義変更ができなるため、調停調書の内容は非常に重要です。
また、調停調書の内容は、裁判でいうところの判決と同様の効力を有するため、原則として後から覆すことはできません。
「調停調書」の内容については、調停が成立する前に自分に不利な条項がないか、相続手続きをとることができるかを確認しておくことがポイントとなります。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
遺産分割調停申立後、調停が不成立の場合

遺産分割調停が不成立となったら、自動的に遺産分割審判に移行します。
特に追加の費用などもかかりません。
遺産分割審判に移行すると、別途書面に提出期日や遺産分割審判期日が設けられることがあるので、裁判所の指示に従って対応しましょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
そもそも遺産を相続したくない場合
遺産分割調停を行わずに、遺産の放棄がしたい場合、「相続放棄」と「相続分の放棄」の2つの方法があります。
相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する手続きとなります。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続放棄の申述期限が過ぎている場合は、「相続分の放棄」を検討することになります。
相続分の放棄は、被相続人のプラスの財産を放棄する手続きです。
相続放棄とは異なり、被相続人の債務を免れる手続きではなく、あくまでプラスの遺産を放棄する趣旨の手続きとなります。
相続分の放棄には、特に期限や書式はありません。
遺産分割調停の当事者となった後に、相続分を放棄することも可能です。
調停中の当事者が相続分を放棄する場合は、家庭裁判所に、相続分放棄届出書兼相続分放棄書、即時抗告兼放棄書、印鑑登録証明書の提出を求められることが多いので、家庭裁判所に確認するとよいでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
調停中の相続税の申告方法

遺産分割調停中に、相続税の申告期限がくる場合は、遺産が未分割の状態(法定相続分どおり)にて、相続税申告を行う必要があります。
調停中だからといって相続税の申告期限が延期されることはないので、ご注意ください。
特に遺産分割調停では、相手方となる相続人との関係性が悪いケースも多いので、同じ税理士に申告を依頼するのか、別の税理士に申告を依頼するのかは、申告期限の2~3か月前には決めておくとよいでしょう。
なお、未分割の状態で申告を行う場合、その申告段階では配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などを受けることができません。
相続税の申告と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出し、相続税の申告期限から3年以内に分割が行われた場合には、分割決定の日の翌月から4か月以内に更正の請求または修正申告を行うことで、特例の適用を受けることができるようになります。
申告期限後3年経過時にも遺産分割が決まらない場合は、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承諾申請書」を提出し、承認を受けることで、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例を受けられる期限が延期されることになります。
「やむを得ない事由」は、遺産分割調停や遺産分割審判の手続き中であることなどがあてはまり、遺産分割協議中であることは理由にならないといわれています。
遺産分割調停が長引いている場合は、上記申請書を提出することを忘れないようにしましょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
まとめ
遺産分割調停は、
- 申立て → 調停期日 → 調停成立/不成立
の流れで進みます。
調停期日では、法的な主張や裏付け資料の提出なども必要となりますので、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
また、遺言書作成をはじめとする生前対策についても、ご自身の財産を遺すうえでどのような点に注意すればよいのか、様々な視点から検討したうえでアドバイスさせていただきます。

遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割に繋がります。
亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査するには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。
また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。
私たちは、複雑な遺産相続の問題をご相談者様にわかりやすくご説明し、ベストな解決を目指すパートナーとして供に歩んでまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力











