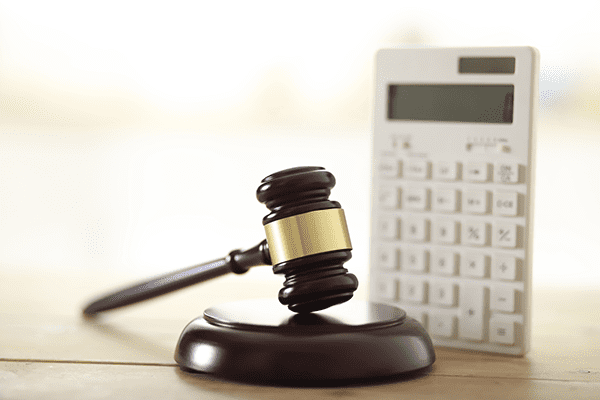各相続人が、具体的にどの遺産を確定的に取得するかを決めるには、遺産分割を経なければなりません。
では、遺産分割は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?
また、遺産分割でトラブルが生じた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、遺産分割について弁護士が詳しく解説します。
遺産分割とは
遺産分割とは、相続人間で確定的に遺産を分ける(分割する)行為です。
相続が起きると、亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産は、原則としていったん相続人全員による共有となります。
しかし、共有状態のままで使い勝手が悪く、トラブルの原因ともなりかねません。
そこで必要となるのが遺産分割です。
遺産分割を行うことで、遺産分割協議の定めに従って、各相続人が単独で遺産を取得できます。
遺産分割の4つの方法
遺産分割には、次の4つの方法が存在します。
それぞれの方法に一長一短があるため、分割方法に迷ったらあらかじめ弁護士へご相談ください。
なお、これらの方法はいずれか一つを選択すべきということではなく、複数の方法を組み合わせることもあります。
現物分割
現物分割とは、相続財産それ自体を分割したり、相続財産一つひとつをそのまま各相続人に割り振る方法です。
現物分割の例として、相続財産が一つの土地であり、相続人が2人いた場合に、その土地を2つに分割してそれぞれの相続人に分けるというものが挙げられます。
また、相続財産が現金、土地、建物であり、相続人が配偶者、長男、長女だった場合、現金を配偶者へ、土地を長男へ、建物を長女へと分けるのも現物分割の一例です。
あるいは、相続財産が預貯金だけであれば、これを相続人で分割します。
メリット
現物分割は、基本的には相続財産一つに対して一人の相続人が相続するため、わかりやすく手続きが比較的簡単です。
デメリット
相続財産に預貯金ではなく不動産などの「もの」が多い場合、各相続人に財産ごとの差が生じてしまう可能性があり不公平感が出やすいです。
換価分割
不動産などを売却して換金し、売却の手続費用などを差し引いたうえで、各相続人に割り当てる方法です。
メリット
換価分割は、相続財産の全部または一部をお金に換えてしまうので、各相続人に公平に分けることができます。
デメリット
- 相続できる土地や建物を売却してしまうので、現物が残らなくなってしまいます。誰かが住んでいる場合などにはよく検討する必要があります。
- 売却の手間と費用がかかります。
- 不動産を売却して利益が生じる場合には、基本的に相続人全員に譲渡所得税が課されます。
代償分割
代償分割とは、共同相続人などのうちの一人が不動産などを相続する代わりに、他の共同相続人に対して生じる相続財産の差を代償金として支払う方法です。
メリット
- 財産や不動産を売却せず引き継ぐことができます。
- 相続人毎に差が生じづらいため公平に分割しやすいです。
デメリット
他の共同相続人との差を埋めるための代償金に加え、場合によっては相続税も支払わなければならないので、大きな負担がかかる可能性があります。
ポイント
代償分割は、3つの方法の中でも争いになりやすい方法です。
この方法を選択される場合には、相続に精通した法律家に相談することをおすすめします。
共有分割
各相続人の持分割合を決めて、共有財産として相続、所有する方法です。
メリット
- 財産や不動産をそのまま残すことができます。
- 不動産などでも公平に分割ができます。
デメリット
- 各相続人の権利関係が複雑になります。
- 財産や不動産を処分したいときに、共同所有者の同意が必要となります。
遺産分割を進める流れ・手順
遺産分割は、どのように進めればよいのでしょうか?
遺産分割の流れや手順は次のとおりです。
遺言がある場合

遺言がない場合

遺産分割調停の進め方

遺言書の有無を確認する
相続が起きたら、はじめに遺言書の有無を確認します。
すべての遺産について帰属先が指定された有効な遺言書が遺っていれば、相続人間で協議をするまでもなく、遺産を分けることが可能であるためです。
遺言書は自宅などで保管することが多いものの、次の場所へ問い合わせることで見つかる場合もあります。
- 公証役場(公正証書遺言の場合)
- 法務局(自筆証書遺言であり、法務局の保管制度を活用していた場合)
- 生前付き合いのあった弁護士などの専門家
- 生前付き合いのあった信託銀行
相続人を確認する
有効な遺言書がなかった場合や、遺言書があっても受け取る人が指定されていない遺産があった場合などには、相続人の確認を行います。
後に行う遺産分割協議を有効に成立させるには相続人全員が参加しなければならず、遺産分割協議に先立って相続人を確定しておく必要があるためです。
相続人の確認は、次の書類などを取り寄せることで行います。
ただし、相続人の状況によってはこれら以外の書類が必要となることもあるため、自分で調査するのが難しい場合には弁護士などの専門家へ依頼するとよいでしょう。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合には、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本及び直系尊属(祖父母等)の死亡の記載のある戸籍など
- 相続人全員の戸籍謄本
なお、これらの書類は、遺産分割協議が成立した後で行う各遺産の名義変更や解約手続きでも使用します。
財産を確認する
相続人調査と並行して、遺産の調査を行います。
遺産分割の対象となる遺産の全容が見えていなければ、次で解説する遺産分割協議をすることが難しいためです。
財産調査の必要書類は遺産の内容によって異なりますが、たとえば次の書類などを確認します。
- 不動産:全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税課税明細書(固定資産税の納付書に同封されている書類)
- 預貯金:預貯金通帳、残高証明書
- 有価証券:取引履歴明細書、残高証明書
- 車:車検証
把握できた遺産は、一覧表などにまとめておくと遺産分割協議の参考資料として活用しやすいでしょう。
遺産分割協議を行う
相続人と遺産が把握できたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分割のための話し合いです。
この話し合いによって、誰がどの遺産を取得するのかを決めていきます。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員による合意が必要です。
相続人全員が合意するのであれば、たとえば「長男が全財産を相続する」など、法律で決まった相続分(「法定相続分」といいます)と異なった遺産分割を行っても構いません。
遺産分割協議がまとまったら、その結果を取りまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。
この遺産分割協議書を使用して、各遺産の名義変更や解約手続きを行います。
一方で、一人でも協議に納得しない人がいる場合には、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割調停
当事者間で遺産分割協議を成立させることが難しい場合には、遺産分割調停を申し立てる必要があります。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う話し合いです。
家庭裁判所の調停委員が当事者から順に意見を聞く形で、話し合いを取りまとめます。
遺産分割調停が1回の期日で成立することはほとんどなく、複数回繰り返されることが一般的です。
期日と期日の期間は1か月程度開くことが一般的であり、遺産分割調停の終了までには数か月から1年程度を要することが多いでしょう。
遺産分割調停はあくまでも話し合いの場であり、家庭裁判所や調停委員が結論を決めるわけではありません。
そのため、相続人同士の意見がまとまらなければ調停不成立となります。
遺産分割審判に移行する
遺産分割調停が不成立となった場合には、遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判とは、諸般の事情を考慮のうえ、裁判所が遺産分割の内容を決める手続きです。
当事者は裁判所が下した審判に不服がある場合には2週間以内に即時抗告しなりません。
遺産分割審判による遺産分割は、法定相続分を原則に、当事者の主張を踏まえ、寄与分や特別受益等が考慮されます。
また、たとえ相続人の多くが自宅不動産を売りたくないと考えている場合であっても、法定相続分どおりに分割するために最適な方法が他にない場合には、換価分割をすべき内容の審判となる可能性があります。
なお、遺産分割では、調停を経ずにいきなり審判を申し立てた場合には、家庭裁判所の判断で調停に回される可能性が高いです。
遺産分割で起こりがちなトラブルと対処法
遺産分割にあたっては、しばしばトラブルが発生します。
遺産分割で起こりがちなトラブルや基本的な対処方法はそれぞれ次のとおりです。
相続人の中に認知症の人がいる
超高齢化社会と言われる昨今、相続人の中に認知症の人がいるケースも少なくないでしょう。
重い認知症であり遺産分割について理解が難しい状態であれば、その人を省いて遺産分割協議を進められると考えるかもしれません。
しかし、遺産分割協議を有効に成立させるには、相続人全員の合意が必要です。
重い認知症の人も相続人である以上、遺産分割協議から除外することはできません。
この場合には、遺産分割協議に先立って家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人とは、本人の生活・医療・介護・福祉など身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護・支援する役割を担う人です。
成年後見人が選任されると、成年後見人が認知症である本人に代わって遺産分割協議に参加します。
なお、成年後見人は認知症である相続人本人の利益のために活動をするため、原則として認知症の人の取り分が法定相続分未満となる遺産分割協議を成立させることはできません。
また、成年後見人は遺産分割協議だけを担うわけではなく、一度選任されたら原則として本人が亡くなるまで(もしくは、能力を回復するまで)継続します。
相続人の中に行方不明の人がいる
相続人の中に、連絡の取れない者がいる場合もあります。
この場合であっても、連絡の取れない者を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。
相続人の中に行方不明の人がいる場合には、まず本当に行方不明であるかどうかを調査する必要があります。
単に他の相続人が連絡先を知らないことと本当に行方不明であることでは、手続きに大きな違いがあるためです。
単に他の相続人が連絡先を知らないという場合には、住民票を調査するなどにより、相続人の所在を把握します。
具体的な調査方法がわからない場合には、弁護士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
調査の結果連絡先が判明した場合には、通常どおり遺産分割協議へ進みます。
一方、住民票上の住所地に居住していないなど、ある程度調査をしても所在がわからない場合には、家庭裁判所へ申し立てて不在者財産管理人を選任してもらうことが必要です。
そのうえで、不在者財産管理人が行方不明である本人に代わって、遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議がまとまらないことも、遺産分割におけるよくあるトラブルの一つです。
一度話し合いがこじれてしまうと、当事者間で話し合いを継続したところで平行線となることが多いでしょう。
そのため、当事者間での協議が難しいと判断したら、早期に弁護士へご相談ください。
弁護士へ依頼すると、まずは弁護士が代理をして相手との交渉を行うことが一般的です。
それでも交渉がまとまらない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判の申立てを検討します。
遺産分割に関する連絡を無視されている
行方不明などではないにもかかわらず、一部の相続人が連絡を無視して遺産分割協議が進まない場合もあるでしょう。
この場合には、弁護士へ相談のうえ遺産分割調停を申し立てて手続きを進めます。
調停を申し立ててもなお相手が調停に現れない場合には遺産分割審判へと移行し、裁判所に遺産分割の内容を決めてもらうこととなります。
遺産分割で困ったらAuthense法律事務所へご相談ください
遺産分割を進めるには、遺産や相続人を確認したうえで遺産分割協議を行います。
しかし、当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合や、一部の相続人が話し合いに応じない場合もあるでしょう。
この場合には、遺産分割調停や遺産分割審判へ移行して解決を図ります。
これらの手続きをスムーズにかつ有利に進めたい場合には、早期に弁護士へご相談ください。
また、生前に遺言書を作成しておくことで、予防できる相続争いも少なくありません。
相続がまだ発生していない場合には、将来のトラブルを予防するため遺言書の作成も検討するとよいでしょう。
Authense法律事務所では、生前の相続対策や遺産分割トラブルの解決に力を入れています。
将来の相続争いを予防したい際や遺産分割でトラブルが発生してお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続に関するご相談は初回60分間無料です。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力